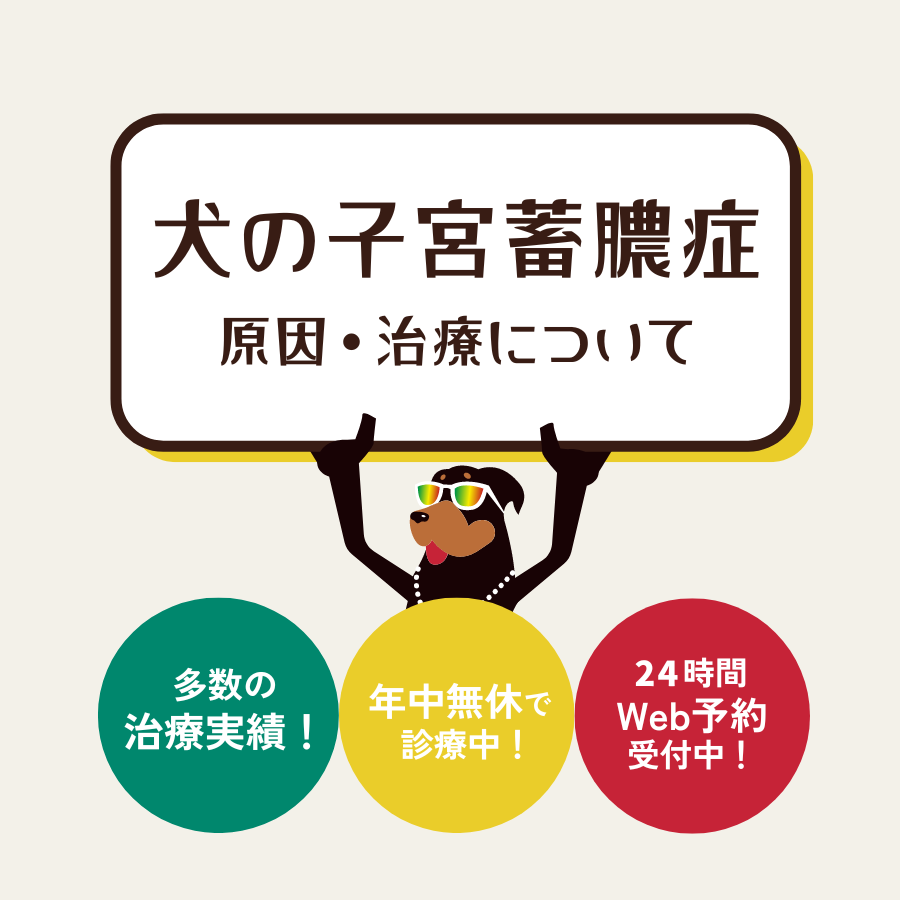
豊橋市、豊川市、新城市、田原市、浜松市、湖西市のみなさんこんにちは。
愛知県豊橋市のオリバ犬猫病院の院長辻元です。
今回は、犬の子宮蓄膿症の症状と原因、当院での治療について説明をさせていただきます。
【犬の子宮蓄膿症】症状・治療・予防法を獣医師が詳しく解説!命に関わる病気とは?
犬の子宮蓄膿症は場合によっては死に至るとても危険度の高い病気です。
「最近、愛犬の様子がおかしい…」
・水をたくさん飲むようになった
・食欲がなく、元気がない
・お腹が膨らんできた
・陰部から膿のようなものが出ている
・何回もトイレに行くが何も出ない
このような症状が見られた場合、「子宮蓄膿症(しきゅうちくのうしょう)」かもしれません。
子宮蓄膿症は、発見が遅れると命に関わる危険な病気です。しかし、早期発見・治療を行うことで助かる可能性が高まります。
本記事では、子宮蓄膿症の原因・症状・治療法・予防法について詳しく解説します。
<子宮蓄膿症とは?>
子宮蓄膿症とは、細菌感染により子宮に膿(うみ)が溜まる病気です。
主に以下の細菌が原因になります。
• 大腸菌
• ブドウ球菌
• サルモネラ菌
子宮内膜が炎症を起こし、大量の膿が子宮内に蓄積してしまいます。
放置すると、膿が子宮を圧迫し破裂する可能性があり、腹膜炎を引き起こして命を落とす危険性もあります。
<子宮蓄膿症の原因と発症しやすい犬猫の特徴>
子宮蓄膿症の発症には、ホルモンの変化が深く関わっています。
犬猫は発情期(ヒート)の後、**黄体ホルモン(プロゲステロン)**が分泌され、子宮内膜が厚くなります。この時期に細菌が侵入すると、免疫力が低下した子宮内で感染が広がりやすくなるのです。
また、以下の要因もリスクを高めます。
✔ 避妊手術を受けていない
✔ 発情期後(約3ヶ月以内)
✔ 高齢(5歳以上で発症リスクが上がる)
✔ 7歳以上では30%の確率で発症すると言われている
犬は閉経がなく、生涯にわたって発情を繰り返します。そのため、避妊手術を受けていない犬は発情期ごとに子宮蓄膿症のリスクが高まるのです。
<子宮蓄膿症の症状>
子宮蓄膿症の症状は、膿が体外に排出されるかどうかによって異なります。
① 開放性子宮蓄膿症(膿が外に出る)
• 陰部から膿や血混じりの分泌物が出る
• 陰部を頻繁に舐める
• 発熱
• 食欲不振
② 閉鎖性子宮蓄膿症(膿が体内に溜まる)
• お腹が大きく腫れる
• 嘔吐・下痢
• 水を大量に飲む(多飲多尿)
• ぐったりして動かない
• 震える・立ち上がれない
特に閉鎖性子宮蓄膿症は危険です!
膿が体内に溜まり続けるため、子宮が破裂し腹膜炎を引き起こす可能性があります。
この場合、緊急手術が必要になるため、早めの診察が重要です。
<子宮蓄膿症の診断方法>
子宮蓄膿症が疑われる場合、以下の検査を行います。
① 血液検査
• 白血球の増加(炎症が起きている)
• CRP(炎症マーカー)の上昇
• 腎機能の異常(重症化すると腎不全を引き起こす)
② 画像診断(レントゲン・超音波検査)
• 子宮が異常に腫れていないか確認
• 開放性か閉鎖性かの判断
レントゲンやエコー検査で、子宮内に膿が溜まっているかを視覚的に確認します。
<子宮蓄膿症の治療法>
① 外科手術(子宮・卵巣の摘出)
最も確実な治療法は、手術による摘出です。
手術では、膿が溜まった子宮と卵巣を完全に取り除きます。
✔ 手術後の再発リスクなし
✔ 根本的な治療が可能
✔ 術後の回復が早い
※ 高齢や基礎疾患がある犬は、麻酔リスクが高まるため慎重に判断します。
↓次の写真は避妊手術にて摘出した正常の子宮卵巣です。

↓次の写真は実際に子宮蓄膿症になり開腹して切除する前の子宮の写真です。
子宮いっぱいに膿が溜まっている事が分かります。


② 内科治療(抗生剤の投与)
手術ができない場合、抗生剤の投与による治療を行います。
✔ 麻酔をかける必要がない
✔ 高齢犬・持病がある犬でも対応可能
ただし、内科治療では根本的に完治しないため、
次の発情期に再発するリスクが高いというデメリットがあります。
<子宮蓄膿症の予防方法>
子宮蓄膿症を防ぐ最も有効な方法は、避妊手術を受けることです。
避妊手術のメリット
✔ 子宮蓄膿症を100%予防できる
✔ 乳腺腫瘍(乳がん)のリスクが下がる
✔ 発情期のストレスがなくなる
手術を行うタイミングは、**初めての発情が来る前(生後6ヶ月〜1歳)**が理想的です。
しかし、成犬や高齢犬でも手術は可能です。
避妊手術にはメリットが多く、子宮蓄膿症を確実に防ぐ方法として推奨されています。
<まとめ>
子宮蓄膿症は、放置すると命に関わる危険な病気です。
特に避妊手術をしていない犬猫は、発情期ごとに発症リスクが高まるため注意が必要です。
【子宮蓄膿症のポイント】
✔ 5歳以上の避妊していない犬猫は要注意
✔ 7歳以上の犬猫は30%が発症すると言われている
✔ 早期発見が命を救う!(おかしいと感じたらすぐに病院へ)
✔ 最も確実な予防法は避妊手術
「最近、愛犬の様子が変…」と感じたら、すぐに動物病院へご相談ください!


